長谷園
- かまどさん(ご飯炊き用土鍋)
- ヘルシー蒸し鍋
- ふっくらさん(蒸し焼き用土鍋)
- 燻製・ロースト・焼肉用(スモーク用土鍋)
- 電子レンジ専用製品特集
- IH対応製品特集
-
 鍋アラカルト
鍋アラカルト
-
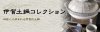 伊賀焼土鍋コレクション
伊賀焼土鍋コレクション
- サーバー・ボトル
- ビアマグコレクション
- ティータイムコレクション
- ほっこりコレクション
- 酒器
- 器

 |
 |

「ほら、いい感じの焼け色だ、今が最高の食べごろだよ!」「そうそう、ささっとくぐらせて、あざやかな緑になったら大丈夫。シャキシャキの歯ごたえがたまらなく旨いぞ。」食卓でワイワイといただく出来たて料理は何とも旨い。
伊賀焼の郷『長谷園』(長谷陶製陶株式会社)は、1832年(天保3年)の創業。
伊賀・丸柱の地に初代当主・長谷源治が開窯してから、180年以上の歴史を誇る、伊賀焼で唯一の「三重県ブランド」に認定された老舗です。
「伊賀焼伝統の技」「今に生きる民具を作る探究心」「伊賀土を生かすものづくりの心」を変わらず持ち続け、
「日常の器だからこそ、こだわりたい。作り手は真の使い手であれ!」をモットーに、楽しさ、おいしさに出あえるさまざまな卓上調理器を作り出しています。
また、1300年程前から続く伊賀焼の伝統と技術を継承しつつ、常に時代を見据えたモノづくりをしています。
『いかに飯をうまく食い、いかに酒をうまく呑むか。』
長谷園の器作りの発想は、この一言からすべてが始まっています。
卓上調理の楽しみは土鍋にとどまらず、「もっと新しい、もっと旨い食べ方があるはずだ・・・」
その一念から炊きたて、蒸したて、いぶしたて、焼きながら、炙りながら、と。
「食卓で○○ながら」の楽しさ・美味しさに出会う様々な調理器を作り出しています。
ひとりでほっこりと、または、大切な家族や親しい仲間たちと囲む「一期一会の食卓」は、こころ弾む楽しい広場です。
食いしん坊が集まって作りあげた長谷園の器の数々で、『究極の遊びの食卓』を創造してください。



伊賀の地は太古の昔、琵琶湖の湖底だったため、炭化した植物を多く含みます。
そのため、高温で焼成すると植物の遺骸だった部分が燃え尽きて細かな空洞ができ、
土鍋本体がしっかりと熱を蓄えて食材の芯までじっくりと火を通すようになり、旨みを逃さずにおいしい料理にしてくれます。
伊賀焼が本格的に発展したのは鎌倉時代からといわれています、伊賀が良質な陶土の山地であること・薪に最適な赤松の森林が豊かであったことが大きな理由です。
陶器生産に欠かせない土と燃料、そのどちらも地元で調達できることはとても恵まれた環境でした。
耐火度の高い伊賀土は、茶人にも愛されてきました。高温の登り窯で何日も焼かれてできる伊賀焼には、
作品の表面に幾重にも降りかかった自然の灰が溶けてガラス状になる「自然釉」と呼ばれる景色が生まれます。
その一期一会の景色が茶道に通じ、茶陶として重宝されたと考えられています。
今でも年に数回炊き上げる登り窯で焼く陶器には、炎の朱色や自然釉といった独自の景色が現れます。
また、この素地は遠赤外線効果も発揮するため、「煮る・焼く・蒸す・炙る」などの調理器具として、昔から多くのプロの料理人に愛されています。
ところで、「プロが好む」=「扱いが難しい」とイメージをしますよね?
しかし、ここが長谷園のスゴイところです!
例え、プロの料理人ではなくとも、ご家庭で、より美味しいご飯を食べてもらえるように、調理やお手入れ方法もシンプルです。
「土もの」は食を美味しくします。
同じ食材でも、鍋が良いと、もっと美味しくなります。

伊賀の山に分け入ると、小さな登り窯の名残がいくつも見つかります。そばには苔生した土鍋や土瓶の破片も

昭和40年代まで稼働していた窯内壁の自然釉(降りかかった薪の灰が溶け、ガラス状に変質する現象)

古い伊賀焼の破片。
「長谷園」の文字が入っています。



弊社の運営する店舗において、日本で唯一の土鍋コーディネーターである、長谷園の竹村氏をお招きし、土鍋を使った料理教室を開催しました。
土鍋というとお鍋を想像する方が多いのですが、毎日の料理で大活躍できるのが長谷園の土鍋のスゴイところ。
簡単な調理で土鍋が美味しくしてくれることに参加された方もびっくりされていました。
 |
||
 |
 |
 |

 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
長谷園
 |
 |
 |
 |
|---|---|---|---|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||
